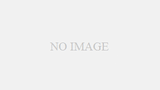5月5日は「こどもの日」として広く知られていますが、それと同時に「端午の節句」という日本の伝統行事でもあります。
この日は、鯉のぼりを飾ったり、粽(ちまき)や柏餅を食べる風習がありますが、それに加えて「菖蒲湯」に入る習慣も長く続いています。
菖蒲湯に浸かることには健康や厄除けの願いが込められていますが、なぜ5月5日に行うのでしょうか?また、頭に菖蒲を巻く理由とは?この習慣の背景にはどのような歴史があるのでしょうか?
この記事では、菖蒲湯の由来や効果、そして正しい入浴方法について詳しくご紹介します。
菖蒲湯に入るタイミングは?
菖蒲湯(しょうぶゆ)に入るのは、端午の節句である5月5日とされています。2025年の場合、この日は月曜日にあたります。特に入浴の時間に決まりはなく、その日の好きな時間に入ることができます。
普段の生活リズムを崩さずに楽しむためにも、いつもの入浴時間に菖蒲湯を取り入れるのがおすすめです。朝風呂派の方は目覚めをすっきりさせる効果が期待でき、夜に入る方はリラックス効果が高まり、ぐっすり眠ることができるでしょう。
家族全員で菖蒲湯を楽しむこともでき、特に子どもにとっては日本の伝統行事を体験する良い機会になります。菖蒲湯を通じて、昔から伝わる風習を学びながら健康を願うことができます。
菖蒲湯の歴史と由来
中国から伝わった菖蒲湯のルーツ
菖蒲(しょうぶ)は古くから邪気を払う薬草として知られています。中国では、5月は特に病気が広まりやすい時期とされ、厄除けや健康祈願のために菖蒲を使う習慣がありました。特に5月5日は「凶日」とされており、この日に菖蒲湯に入ることで無病息災を願うようになったといわれています。
この習慣が日本に伝わったのは奈良時代(710~794年)とされ、当時は田植えの前に女性が身を清める「五月忌み(さつきいみ)」と呼ばれる風習がありました。これと中国から伝わった端午の節句の文化が融合し、菖蒲湯の風習が生まれたと考えられています。
武士文化と菖蒲湯の関係
鎌倉時代(1185~1333年)になると、武士の文化が発展しました。その中で「尚武(しょうぶ)」という言葉が、「菖蒲(しょうぶ)」と同じ読み方をすることから、端午の節句は「男の子の成長を祝う日」として認識されるようになりました。こうして、健康と強さを願う行事として菖蒲湯が定着し、端午の節句は「菖蒲の節句」とも呼ばれるようになりました。
菖蒲の種類と読み方
菖蒲は「しょうぶ」と「あやめ」という2つの読み方がありますが、実は異なる植物です。「あやめ」はアヤメ科の植物で、乾燥した土地で育ちます。一方、「しょうぶ」はサトイモ科に属し、湿地や水辺に生育するのが特徴です。
端午の節句で使用するのは「しょうぶ」の葉であり、「花菖蒲(はなしょうぶ)」とは異なります。花菖蒲は観賞用として栽培されている植物であり、菖蒲湯には適していません。購入する際には、間違えないよう注意しましょう。
菖蒲湯の効果とは?
菖蒲湯には、次のような健康効果があるとされています。
- 血行促進・保湿作用
- 疲労回復・リラックス効果
- 内臓の働きをサポート
- 殺菌・解毒作用
- 冷え性の改善
- 肩こりや腰痛の緩和
- 神経痛や筋肉痛の軽減
特に、菖蒲に含まれる精油成分は血行を促進し、体を温める働きがあります。寒い時期はもちろん、初夏の季節でも疲れた体をリフレッシュさせるのに役立ちます。
菖蒲湯の正しい入り方
菖蒲湯の作り方
菖蒲湯の準備はとても簡単です。スーパーや花屋で販売されている菖蒲をそのまま湯船に浮かべるだけで、簡単に楽しむことができます。
また、以下の方法を試すことで、より効果的に菖蒲湯を楽しむことができます。
- 菖蒲の葉を細かく刻み、ネットや布袋に入れてお湯に浸す
- 菖蒲の茎を折って香りを引き出し、お湯に成分を溶け込ませる
特に、小さな子どもや赤ちゃんがいる場合は、直接葉が肌に触れないようにネットに入れると安心です。
菖蒲を頭に巻く理由
「菖蒲を巻いた部分が良くなる」という言い伝えがあり、特に頭に巻くことで「知恵がつく」と考えられています。また、菖蒲の成分が肌に直接触れることで血流を良くし、健康促進の効果があるともいわれています。
他にも、お腹に巻くことで内臓の働きを良くしたり、手足に巻いて冷え対策をしたりと、さまざまな使い方があるようです。
菖蒲湯の英語表現
英語圏には菖蒲湯の習慣がないため、直訳すると「a sweet-flag bath」となります。
まとめ
菖蒲湯は、健康と厄除けを願う日本の伝統行事のひとつです。古代中国から伝わったこの風習は、日本独自の文化と融合し、現代にまで受け継がれてきました。
5月5日の端午の節句には、ぜひ家族みんなで菖蒲湯に入り、心と体をリフレッシュしながら、昔ながらの日本の風習を楽しんでみてはいかがでしょうか?