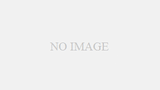2019年4月9日、日本政府は1万円札、5千円札、千円札のデザイン変更を発表しました。では、新しい紙幣の使用開始時期はいつなのでしょうか? また、新しい紙幣に描かれる人物たちはどのような功績を残したのでしょうか? ここでは、新紙幣の発行日やデザインの特徴、そして肖像に選ばれた偉人たちについて詳しく解説します。
日本の紙幣の歴史
日本において初めて紙幣が使用されたのは1334年といわれていますが、その現物は確認されていません。現存する最も古い紙幣は、江戸時代の1610年頃に伊勢の商人によって発行された「山田羽書」です。この紙幣は約250年間、流通しました。
江戸時代には、「藩札」と呼ばれる藩独自の通貨が流通し、さらに「旗本札」や「町村札」、「私人札」など地域ごとに異なる紙幣が存在しました。しかし、これらの紙幣は全国的に使われるものではありませんでした。
全国で共通して使われる紙幣が登場したのは明治時代に入ってからです。1868年に明治政府が「太政官札」を発行しましたが、偽造が横行し、流通が困難となりました。その後、1872年にドイツの技術を用いた「明治通宝」が発行され、1899年には政府紙幣が廃止され、銀行が発行する「銀行券」へと移行しました。
1882年、日本銀行が設立され、以降、日本銀行が紙幣の発行を独占するようになりました。最初に紙幣の肖像に採用されたのは、1881年発行の1円紙幣に描かれた「神功皇后」でした。その後、菅原道真や聖徳太子などが紙幣に登場しましたが、戦後にはGHQの指示で肖像の変更が行われました。
近年では、福沢諭吉、新渡戸稲造、夏目漱石などが紙幣の肖像として採用されています。紙幣の肖像は、日本の文化や歴史に大きな影響を与えた人物が選ばれることが多く、時代ごとに異なる価値観を反映したものとなっています。
新紙幣の発行日
財務省と日本銀行は、2024年7月3日 に新紙幣(一万円札、五千円札、千円札)を発行すると発表しました。
紙幣のデザインは約20年ごとに刷新される傾向があります。その理由の一つが、「偽造防止技術の向上」です。日本の紙幣は偽造防止技術に優れていますが、長い期間が経つと偽造リスクが高まるため、新たな技術を導入し、安全性を確保する必要があります。
もう一つの理由は、「技術の継承」です。紙幣の製造技術は、長期間変更がないと技術者の技術継承が困難になります。そのため、一定の周期でデザインを更新することが必要とされています。さらに、新紙幣の導入には社会の変化に対応する目的も含まれており、視覚障がい者のための工夫や、より使いやすい設計が取り入れられることもあります。
新紙幣のデザインと肖像
一万円札
- 肖像:渋沢栄一
- 裏面デザイン:東京駅丸の内駅舎
五千円札
- 肖像:津田梅子
- 裏面デザイン:藤の花
千円札
- 肖像:北里柴三郎
- 裏面デザイン:葛飾北斎の「富嶽三十六景・神奈川沖浪裏」
肖像に選ばれた偉人たち
渋沢栄一
「日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一(1840-1931)は、実業家として500以上の企業の設立に関わりました。第一国立銀行(現・みずほ銀行)、東京株式取引所(現・東京証券取引所)、帝国ホテル、東京海上保険(現・東京海上日動)など、日本の経済基盤を築く重要な役割を果たしました。彼の考え方は「道徳経済合一」として知られ、利益追求と社会貢献の両立を重視していました。
津田梅子
日本の女子教育の先駆者である津田梅子(1864-1929)は、6歳でアメリカへ留学し、帰国後に女子英学塾(現・津田塾大学)を創設しました。当時の女性教育のあり方に変革をもたらし、日本における女性の自立と教育の発展に貢献しました。彼女の教育理念は、単なる知識習得だけでなく、自立した女性の育成に重きを置いていました。
北里柴三郎
感染症研究の第一人者である北里柴三郎(1853-1931)は、ペスト菌の発見や破傷風の血清療法の開発を行い、「日本の細菌学の父」として知られています。慶應義塾大学医学部の創設にも関わり、日本の医療発展に大きな影響を与えました。彼はまた、細菌学の研究だけでなく、公衆衛生の向上にも尽力し、多くの人々の健康を守るための施策を推進しました。
まとめ
新紙幣は2024年7月3日に発行されましたが、以前に発行されて使用してきた紙幣も引き続き使用可能です。新紙幣発行を口実にした詐欺行為には十分注意しましょう。また、新しい紙幣は、現行のものと比べてセキュリティ機能が強化され、より安心して使えるよう設計されています。新紙幣の発行を機に、日本の通貨の歴史や背景について改めて考える機会になるかもしれません。