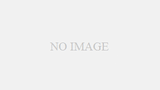「NHKのど自慢」は、毎週日曜日のお昼に放送されている長寿番組で、多くの視聴者に親しまれています。
この番組では、全国各地から集まった一般の人々が、自慢の歌声を披露し、その出来栄えを鐘の音で評価されるという独自のシステムを採用しています。
出演者たちは、自ら選んだ楽曲を熱唱し、会場の観客と審査員の前でその歌唱力を発揮します。
しかし、ただ歌を披露するだけではなく、番組ならではの演出が魅力の一つとなっています。
鐘の音によって評価が決まるこのスタイルは、番組の大きな特徴であり、視聴者が楽しみにしている要素でもあります。
では、一体この鐘にはどのような意味が込められているのでしょうか?
また、「NHKのど自慢」という番組が誕生した背景や歴史についても詳しく解説していきます。
NHKのど自慢の番組概要
「NHKのど自慢」は、NHK総合テレビおよびNHKラジオ第一で毎週日曜日に生放送される番組です。
日本全国各地で公開収録が行われ、地域ごとの特色を生かした会場で開催されるのが特徴です。
基本的に、中学生以上のアマチュア歌手が参加可能であり、毎回18組の出場者が選ばれます。
参加者は、それぞれが思い入れのある楽曲を披露し、その歌唱力が鐘の音によって判定されることになります。
審査の結果、「合格」と判断された参加者の中から最も優れた1組が「チャンピオン」、もう1組が「熱演賞(審査員特別賞)」に選ばれます。
さらに、チャンピオンとして選ばれた人たちの中から、特に素晴らしいパフォーマンスを見せた12〜15組程度が、年に一度開催される「チャンピオン大会」に進出することができます。
この大会では、年間で最も優れたパフォーマンスを披露した出場者が「グランドチャンピオン」として表彰され、準優勝者には「優秀賞」が授与されます。
こうした仕組みにより、アマチュア歌手の夢を応援する場として、多くの人々に愛され続けているのです。
NHKのど自慢の歴史
「NHKのど自慢」の歴史は、戦後間もない昭和21年(1946年)1月19日に放送が開始されたラジオ番組「のど自慢素人音楽会」に端を発します。
この番組は、戦後の混乱期にあった日本に明るさと希望をもたらす娯楽として、多くの人々に親しまれました。
翌年には「のど自慢素人演芸会」と改称され、昭和28年(1953年)3月15日からはテレビ放送もスタート。
当初はラジオとテレビの同時放送という形が取られ、より多くの人々に楽しんでもらえる番組へと進化しました。
昭和45年(1970年)になると、番組名が「NHKのど自慢」に変更され、公開生放送の形式が基本となりました。
また、NHKでは昭和35年(1960年)にテレビのカラー放送を開始していましたが、「NHKのど自慢」は全国各地からの中継が主となるため、しばらくの間は白黒放送が続いていました。
しかし、昭和46年(1971年)4月には、ついにカラー放送へと移行。
このタイミングで、より華やかで視覚的にも楽しめる番組へと変わっていきました。
平成27年(2015年)には放送70周年を迎え、これを機に、これまで高校生以上とされていた参加資格が中学生以上に引き下げられました。
現在では、日本国内だけにとどまらず、「NHKワールド・プレミアム」や「NHKワールド・ラジオ日本」を通じて海外でも視聴可能になり、日本の文化を世界に発信する番組の一つとなっています。
鐘の名前と鳴らされる回数の意味
番組の冒頭や出場者の評価時に鳴らされる鐘は、「チューブラーベル」という正式名称を持っています。
この鐘は、番組のシンボル的な存在であり、視聴者が「NHKのど自慢」と聞いて最初に思い浮かべるものの一つでしょう。
また、鐘の音は「チャイム」「シンフォニック・チャイム」「コンサート・チャイム」「オーケストラ・チャイム」などと呼ばれることもあります。
鐘の鳴らされ方は、3つのパターンがあります。
① 合格の鐘
「ドシラソ ドシラソ ド ミ レ」と長く鳴る鐘の音は、「合格」を意味します。
この鐘が鳴った出場者は、歌唱力が高く評価され、次の段階へ進むことになります。
② 不合格の鐘
「ド レ」と2回だけ鳴らされる場合は、「不合格」を表します。
この鐘が鳴ると、出場者は残念ながら次のステップには進めませんが、それでも堂々と歌を披露したことは貴重な経験となるでしょう。
③ 特殊な不合格の鐘
まれに、「ド」と1回だけしか鳴らされないことがあります。
この場合、会場を盛り上げるために参加した人や、極度の緊張で歌詞を忘れてしまった人、あるいは音程が大きく外れてしまった人に対して鳴らされることが多いようです。
合格・不合格の判定を行うのは、音楽プロデューサーや音楽ディレクター、放送地域のNHK番組責任者など、通常5名の審査員。
彼らは別室でモニターを通して出場者のパフォーマンスをチェックし、鐘の回数を決定。
鐘を鳴らす奏者にタイミングを指示する仕組みになっています。
1月19日は「のど自慢の日」
昭和21年(1946年)1月19日に「のど自慢素人音楽会」の放送が開始されたことを記念し、この日が「のど自慢の日」と制定されました。
「NHKのど自慢」は、ラジオ番組として誕生し、現在ではテレビ放送や海外放送まで展開される国民的番組に成長しました。
この番組がきっかけでプロの歌手としてデビューした人も数多くいます。
例えば、北島三郎、美空ひばり、五木ひろし、Kiroroの玉城千春、ジェロなど、のちに日本の音楽界で大きな活躍を遂げたアーティストたちが、この舞台を経験しました。
これからも、「NHKのど自慢」は、多くの才能を発掘し、新たなスターを生み出し続けるでしょう。
まとめ
「NHKのど自慢」は、日本の音楽文化を支える長寿番組として、多くの人々に親しまれています。
全国各地で開催される公開収録は、その地域ごとの魅力を伝える場にもなっており、視聴者にとっては毎週楽しみなイベントのひとつです。
この番組の大きな特徴である鐘の音は、単なる評価の道具ではなく、出場者の努力や個性を際立たせる重要な演出のひとつです。
鐘の音を通じて、緊張感と期待感が生まれ、見ている人々も一緒になって応援したくなる雰囲気が作り出されています。
また、戦後から続く歴史ある番組として、これまでに数多くの才能を輩出してきました。
プロの歌手として活躍するアーティストの中にも、「NHKのど自慢」をステップに飛躍した人が多数います。
この番組が、一般の人々に夢と希望を与える場であり続けることは、今後も変わらないでしょう。
時代の変化とともに番組の形も進化していくかもしれませんが、「歌を通じて人々をつなぐ」という本質はこれからも大切にされていくはずです。
これからも「NHKのど自慢」がどのように発展し、どんな新しいスターを生み出していくのか、楽しみに見守っていきたいですね。